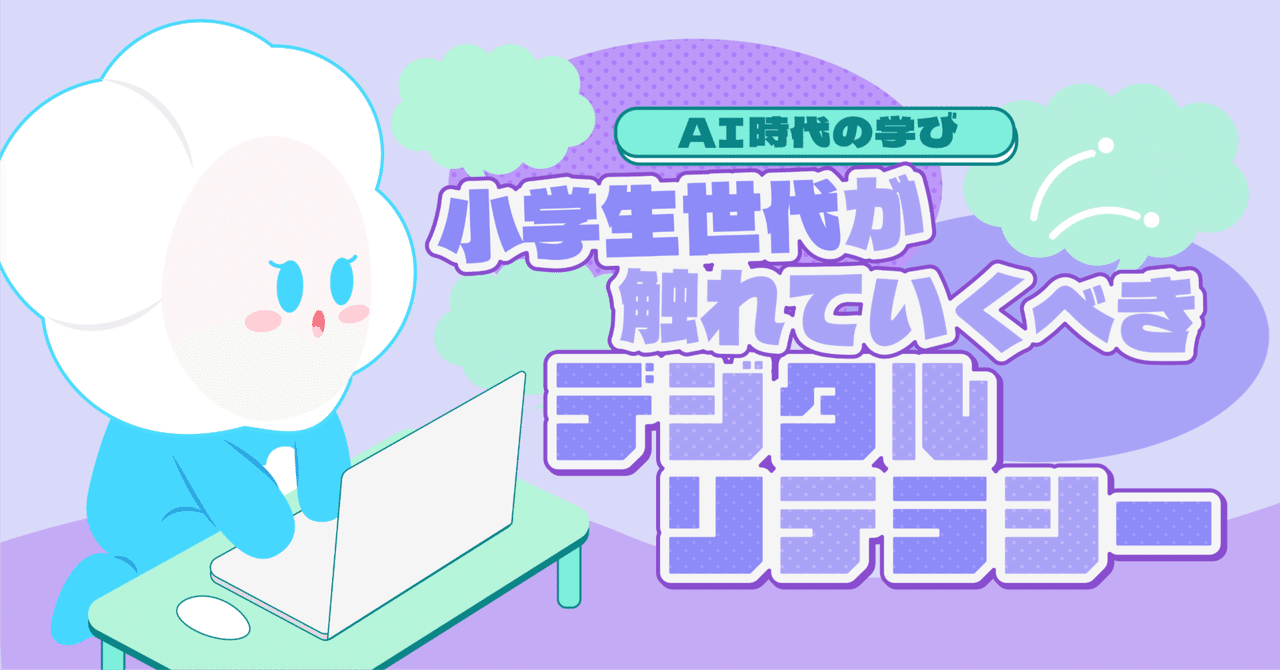AIや生成ツールが日常に入り込み、社会の仕組みそのものを変えつつある今。
「デジタルネイティブ」と呼ばれる小学生世代にこそ、情報をただ“使う”だけでなく、“見極めて活かす力”が求められています。
実際のところAIは未だ「完璧」とは言えず、最終的には人間の手による修正やチェックが欠かせません。
インターネットの情報を鵜呑みにしない判断力、オンライン上で自分を守る安全意識、そしてデジタルを学びや表現に結びつける創造力。これらはまとめて「デジタルリテラシー」と呼ばれ、これからの時代を生きる子どもにとって、読み書きや計算と同じくらい大切な基礎になりつつあります。
■情報を鵜呑みにしない判断力
ネットで調べれば欲しい情報はすぐ出てきますが、その中身はピンキリ。
保護者としてできるのは、子どもと一緒に「この記事は誰が書いたの?」「別のサイトでも同じことを言っているかな?」と話す・確かめる習慣を持つことです。
例えば学校の調べ学習でいくつかのサイトを比較して、「信頼できそうな情報だけまとめてみよう」と声をかけるだけでも、リテラシーを高める練習になります。
同様に、ChatGPTやGeminiなどのAIツールを用いた検索も注意が必要です。これらはインターネット上の情報を手軽に分析・収集し回答を生成してくれる便利なツールではありますが、正確性が担保されているわけではありません。やはりAIによる情報提供に関しても、出典を確かめる習慣をもつことが重要と言えます。
■自分を守る安全意識
インターネットは便利な一方で、危険も潜んでいます。フィッシングや個人情報の流出、見知らぬ人とのやり取りなど、子どもにとっては身近なリスクが盛りだくさん。だからこそ、安全のための基本的なルールを早めに伝えておきましょう。
本名や住所、学校名は書かない/顔や居場所がわかるような投稿はしない
SNSやチャットで言葉遣い、発言内容に気をつける
知らない人からの連絡には応じない
フィルタリングやペアレンタルコントロールを利用する
実際に、小学生では97.2%、中学生では98.1%の児童・生徒がインターネットを利用しているという調査もあります。(出典:こども家庭庁「青少年のインターネット利用環境実態調査」2024年度版)
スマホを持つ子どもが増える中で、家庭でのルールづくりを今一度見直すべきかもしれません。
■学びや表現に結び付ける創造力
デジタルリテラシーは「危険から身を守る」ためだけのものではありません。学びや表現を広げるため、デジタルコンテンツを有効活用する力でもあります。
調べ学習にオンライン辞書や学術サイトを取り入れる
夏休みの自由研究でAI翻訳や画像生成ツールを試してみる
音楽アプリで短い曲を作る
描画アプリでイラストを描いてみる
こうした体験は、子どもが「デジタルは怖いもの」ではなく「便利で楽しいもの」と感じるきっかけになります。そして興味の分野が広がることで、自分で探求したくなる姿勢を育てることにもつながります。
■デジタルリテラシーを育てるために意識したいこと
ステップを踏む:まずは「検索 → 比較 → 選択」といったシンプルな流れから始める
親も一緒に学ぶ:保護者が判断の基準を見せることで、子どもが“モデル”を持てる
失敗を学びに変える:誤情報に引っかかった経験も「こういうことがあるんだね」と共有して学びにする
▼そこで、KIDSJAPANができること
とはいえ、家庭だけでデジタルリテラシーを育てるのは簡単ではありません。学校の授業では十分にカバーできず、保護者も「どこから教えればいいのか分からない」と感じることが多いのが実情です。
KIDSJAPANは、子どもたちが安心してデジタルで学び、正しくインターネットを活用できる力をつけることができる教育プラットフォームです。
オンラインで完結するため送迎の負担なし
プロ講師によるレッスンで、安全な情報活用や創造的な学びをサポート
AIによるレッスン提案機能で、子どもの興味や成長段階に合わせた個別最適な学びを提供

ただの習い事探しプラットフォームではなく、「これからの時代を生き抜く基礎力」を家庭と一緒に育てていくパートナー。それがKIDSJAPANです。
■本件に関するお問合せ先
運営会社:株式会社キッズジャパン
TEL:03-5405-8800
メール: [email protected]
サービスサイト: https://kidsjapan.jp